September 10, 2011 8:18 PM
粉引汐景茶碗のできるまで。
先日納品を終え、ホッと一息。この度作った粉引茶碗がどのようしてできるか、製作過程をまとめてみました。

まずは原料を採取。
料理と同じく、できるだけ素材をを生かし、好みの味(古陶大好きです)に仕上げたいと思います。

採取した原料の鉄分を除き、砕く!
ある程度砕いたら、ポットミル(左下)に入れてカラカラまわす。
数時間後、ミルからだして篩いで漉す。

暫く置いて粘土を沈殿させ,、上水をきり、乾燥させていく。
程よい堅さになったら、土を練る。
それからロクロを挽く。適度に乾燥させ、高台を削る。

ある程度乾燥させ、化粧土をかける。水分を含みまた膨張する。
再び適度に乾燥させ、釉薬をかけると、また膨張する。
下の画像は、素地→化粧土→釉薬
この間、膨張と収縮をくりかえす、収縮のさい、化粧土と釉薬が素地と一緒に縮んでいかないと剥離してしまう。
右上画像は、釉薬を掛けて置くときに隣にくっついてしまった・・・金海の猫描きもこの状態の時に藁のようなものがあたってできたと思う。(食器の場合は、一度素焼きをしているのでこういうことは起こらない)
釉薬をかけ終えたら、ゆっくりと乾燥させる。完全に乾いたら窯につめ、焼成。焼加減は理想に近づけるよう毎回工夫する。

窯からだし、高台についたより土を外す。
手に当たらないよう、砥石と耐水ペーパーで高台をきれいにする。

粉引汐景茶碗の出来上がり。
泥が、茶碗になりました^^
Trackback (0)
Trackback URL: http://www.utuwa-ya.jp/mt/mt-tb.cgi/3081
Comments (8)
Post a Comment
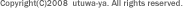


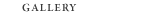
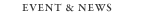
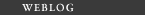

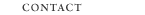
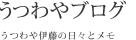




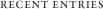


お見事!
いや~どーも、お恥かしい。
いつもながら、素晴らしいですね。
原料からこだわるからこそ、美しい物は出来るのでしょうね。
土から採取されているとは驚きました。
これまで知らずに使っておりゴメンナサイ!
こだわりの粉引ちゃんに一層愛着が湧いてきました。
刷毛目くんもゆっくり成長しています。
出泥の誉っていうんでしょうかね?
hiroさん、ありがとうございます。
欲深いわたしは、使いこむと美しさに一段と磨きがかかり、さらに魅力が増して・・・って思ってます(笑)
mi-re yoshidaさん、コメントありがとうございます。
是非、今後も愛情をそそいでやってください~。
土嚢1袋約20キロ、担ぐの結構大変ですよ。
四月亭さん、学習になりますよ(笑)
出泥の誉とは「器は泥より出でて、泥よりも堅し」
こんな感じですね!
はじめまして、いつもブログ楽しく拝見させていただいております。及ばずながら、私も原土から本歌に近い粉引きを目指して日々奮闘しています。
基本的な質問で恐縮ですが、原土の脱鉄はどのようになさっていますか?いい方法がありましたらご教示いただければ幸いです。
はじめまして、コメントありがとうございます。
この時の脱鉄は、2枚目の画像上部のように、ノミとカナヅチで鉄の部分を除いていきます。
http://www.utuwa-ya.jp/blog/assets_c/2011/09/20110910shiogechawan02.html
(左上画像が鉄が残ってる→右上が鉄を除いたもの)
ものすごく手間のかかる地道な作業をしています。あまり参考にはなりませんね(汗)